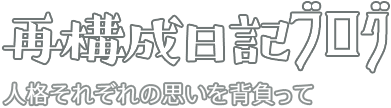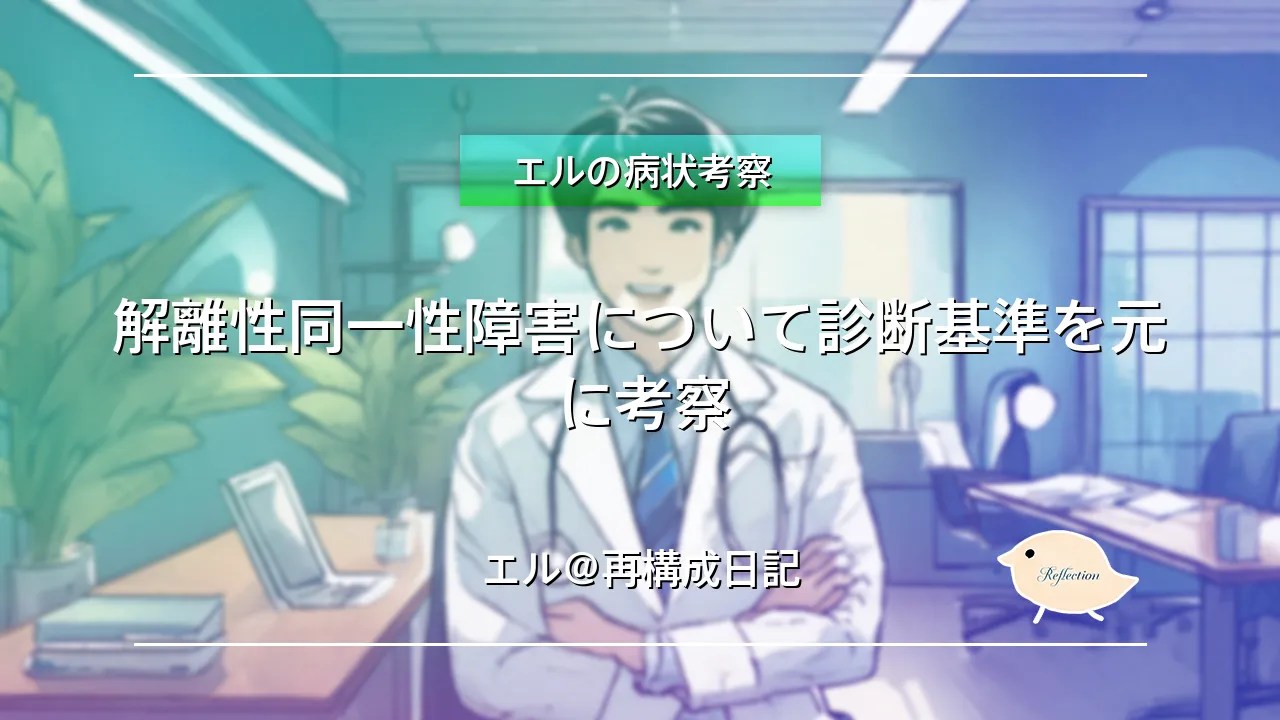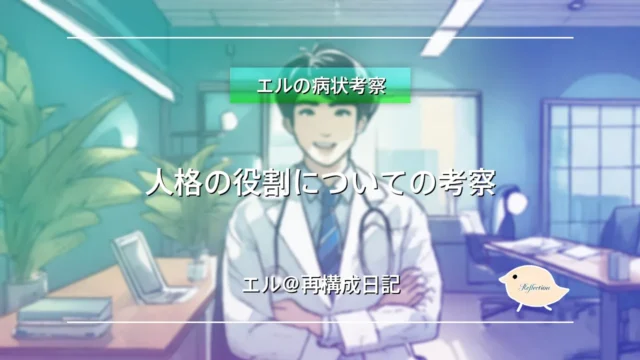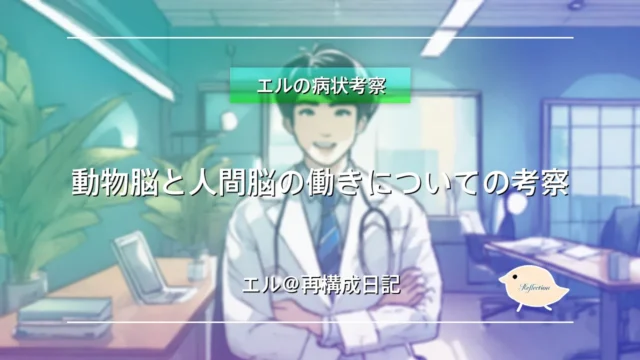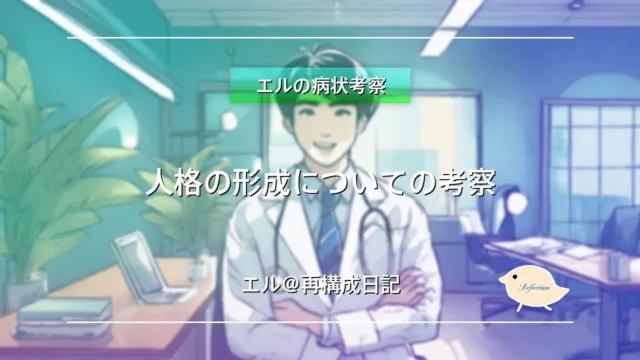今回は、解離性障害並びに、解離性同一性障害の誤解について診断基準を元にして正していこうと思う。考察の分野に入るので、今回もこの一文を入れておく。俺は医者ではないので注意してほしい。
:: はじめに
第一に、解離性障害全般について話さなければならない。解離性同一性障害は、解離性障害の区分の中の1つであり、解離性障害の括りの中で最も重い障害であることを明記しなければならない。そのため、解離性障害のことをまず知ってもらうことが大事だと考える。
※DSM-5によると、『解離性症群』と記載されているが、ここでは一般的ではないので『解離性障害』と記載させていただく。
:: 解離性障害とは
解離性障害の特徴としては次の通りとされている。
意識・記憶・同一性・情動・知覚・身体表象・運動制御・行動の正常な統合における破綻および不連続である。
難しく書いてはいるが、
- 意識
- 記憶
- 自分が一つであるという自我(同一性)
- 感情の揺さぶり(情動)
- 感覚過敏等で使われる五感(知覚)
- 震え(身体表象)
- 動けない(運動制御)
…など、行動において、自分と意図しない現象が起きている状態のこと、または混乱する状態のことを指しているわけだ。簡単に言えば『どうしてこんな状態になっているか分からない』が出てくる障害であるということだな。
解離性障害というものは本人の意図しない事ばかりが起きる障害であると考察する。この症状が出る理由は、DSM-5にはクソ長く書いてあるけれど、本人の心理状態が「複雑性PTSDが密接に絡んだ心理状態であることが原因」とされているように俺には見受けられた。
それらに追従して、様々な解離症状と呼ばれる症状が起きている。そのうちの1つとして、解離性同一性障害というものがある。これまで深く書いてきたけれど、前回の「解離性同一性障害とは」という考察にこちらのことは詳しく記載しているので参考にしてほしい。
:: 解離性同一性障害の診断基準
さて、ここから解離性同一性障害の診断基準というものをDSM-5に則って解説していこうと思う。DSM-5によると、解離性同一性障害の特徴は次のように書かれている。
- 2つまたはそれ以上の区別出来るパーソナリティ状態の存在
- 反復する解離性健忘のエピソード
難しく書かれているわけだが、簡単に纏めていく。
◆ 2つまたはそれ以上の他と区別出来るパーソナリティ状態の存在
これは、「本人とは別人格と言える存在が確認できるか?」ということを指している。別人格とは本人とは明らかに違う存在。性自認の違いや、声の違いなどの身体的な変化、考え方、主張の違い等の事を言う。他人から見て『明らかに違う人と思われる存在』とも言える。
◆ 反復する解離性健忘のエピソード
これは、別人格の出ているときの記憶が抜けている、またはその前後の記憶がないなど、記憶に抜けがあることを指している。なので、診断基準をざっくり説明すると、「別人格の存在が確認できること」と「記憶の抜けが確認されること」の2点に焦点が当てられている。これがDSM-5で定義されている内容だと俺は考えている。
だから、病院に行って、主に先生が確認するのはこの2つだ。DSM-5を元にした場合によるけど。
:: 苦痛や機能の障害がなければ障害とは言えない
そして、当たり前のことだが、「その症状は臨床的に意味のある苦痛または社会的・職業的・その他重要な領域における機能の障害を引き起こしていること」、とDSM-5の診断基準の中には書かれている。解離性同一性障害の症状がある場合でも、生活に困ってないとか、苦しくない、辛くないようだったら解離性同一性障害とは言えない、と明記されている。
これは障害全てに当てはまるが、その症状や状態によって本人に苦痛を伴ったり、社会的に困難な環境になってしまったりすることを障害というものであって、それが無ければ問題はない。なので、様々な解離症状があったとしても、それが社会的に問題も無く、生活にも困らず、自分の苦痛にもなっていなければ、それは障害にはなり得ない。だから、「もし自分がそうなんじゃないか?」という不安に駆られたとしても、それが大きな問題ではなければ解離性同一性障害とは言えない。
:: DSM-5の「作為症と詐病」について
この定義をした上で、DSM-5の「作為症と詐病」という項目も確認していこう。ここは最も意見が分かれるところだからだ。
多分、罹患者も未診断の方も、この分野は一度は話したことがあるのではないか?自分は解離性同一性障害ではないか?と疑っている人にもこの部分は必要かと思う。解離性同一性障害を装う人は、通常この障害の特徴である侵入という微妙な症状を述べない。代わって、この障害についての各種メディアの情報を拠り所にして芝居掛かった解離性健忘やメロドラマのような行動の切り替えといった症状を過剰に報告する傾向がある。と書かれている。
:: 「侵入という微妙な症状」の特徴的な表現と解釈
ここを詳しく説明すると上記の通り、このブログ自体も各種メディアの情報の拠り所にされてしまう可能性があるので、一部だけを抜粋して書かせていただいた。
ただ、よく分からないと思うので、『侵入という微妙な症状』のことだけ説明しようと思う。
侵入とは、俺の解釈にもよるけれど、『心の感情の大きな変化、突発的な変化のこと』を指すのではないかと考察する。
- 楽しい時間なのに突然悲しくなる…
- 安心できる人と一緒に居るのに、いつもと違う不安に襲われる…
- なんだかよく分からないが気持ちの反転が繰り返し起こる…
このような形で、自分の感情のはずなのに感情の制御がうまくいかない、その理由もわからない、その感情の突発的な変化が、『別人格の侵入』という形で書かれているのではないかと俺は推察する。これが『侵入という微妙な症状』なのではないかと、経験上そう思う。
:: DSM-5を読むということ。詐病のリスクと精神疾患の複雑さ
DSM-5を読むということは、簡単に詐病を作り出せるということにもなるので、正直本当はオススメはしないし、こういう機会でもなければ、中の文章を抜粋したりはしない。なんせ、この診断基準に書かれていることを学べば、「医者を騙す技術を習得している」と言っても過言ではないからだ。
医者もこれで勉強する人は多い。参考にしている人も沢山いる。だから、この本は、ぶっちゃけ禁書なみにやべえ物である、というのは分かっている。
さっきも書いたが、各種メディアの情報を拠り所として、ありもしない障害や症状を作り上げてしまう人がとても多い。身体であれば明確な診断基準がある。数値で出てくる。しかし精神疾患の場合は、そんな物がない。数値化できない。そのため、周りの意見や本人の主張を元に診断することになる。
しかし、残念なことに精神疾患の方は、自己暗示というものにかかりやすい傾向の人が多い。そのため、こういうのを学ぶということはとても危険が伴うということも分かって欲しい。
:: 誤解と注意喚起
解離性障害または解離性同一性障害をおもちゃのようにする人たちは、ネットにごまんといる。
多重人格、とてもおもしろい題材だ。それ故、なりたい人も多くいるし、解離性同一性障害の人と知り合ったがために、それは自分の症状なのかも知れないと錯覚し、自ら障害を作り上げてしまう人も、また多いのも事実。近年では、検索しようと思えばいくらでも症状や根拠のない診断テスト、当事者の声は出てくる。
でも、その症状をトレースし、自分の物にしてはいけない。その症状に惑わされてしまってはいけない。障害を持っていることを楽しんでいてはいけない。障害は障害でしかなく、それによって不利益のほうが多いのは確かで、障害を持っていることで楽ができるなんて、そんなわけがない。
:: 解離性同一性障害への向き合い方と覚悟
解離性同一性障害を疑っている人に問う。
- 今より酷い状態だと社会に認知されたいですか?
- その障害を持っているという風に医者に言った途端、拒否される可能性があることを考えていますか?
- 薬が全く効かない、なんていう事実を受け入れられますか?
- 頼りどころのない手探りの状態で、この病気と向き合わなくてはならない覚悟ができていますか?
障害・病気は遊びじゃない。以上エルでした。